近い将来に起こるだろうと言われている南海トラフ地震。
過去に大きな地震の被害を受けたことがある宮城県・仙台市は安全なのか不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、南海トラフ地震が発生したときに宮城県・仙台市に影響はあるのかや、震度予想をご紹介します。
▼この記事で紹介していること
また、今後宮城県に大きな地震が発生する確率や、南海トラフ地震で危ないと言われているエリアはどこなのかも調査したので参考にしてみてくださいね。
南海トラフ地震で宮城県は安全?
宮城県といえば2011年に起こった東日本大震災で、揺れや津波による甚大な被害を受けたことが印象的ですよね。
そのため、近々起こるだろうと言われている南海トラフ地震でどのくらい被害を受けるのか不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
内閣府が発表している震度分布では、宮城県のほとんどの地域で地震の被害が出ないとされています。(参考1):内閣府防災情報のページ-南海トラフの巨大地震による津波高・震度分布等
そのため宮城県は、南海トラフ地震が起こっても建物の倒壊などの可能性が低く、安全な地域だと言えるのですが、海に近いエリアでは津波には警戒が必要かもしれません。
仙台市は大丈夫?
都心部となる仙台市も宮城県のほかのエリアと同様に、南海トラフ地震での震度は3以下のごく小さいものだと予想されます。
そのため、南海トラフ地震での直接的な被害は少なく、普段通りの暮らしができのではないでしょうか。
津波に関してもそれほど心配はいりません。
仙台市では東日本大震災の経験を活かし、海岸堤防やかさ上げ道路などの多重防御施設の整備が進められてきました。
さらには津波が発生しても利用できる避難場所の確保もなされているため、以前よりも震災に強い町になっていると言えそうです。

住民が高い防災意識を持っているのも安心できるポイントだよ。
南海トラフ地震|生き残る宮城県の地域は?
南海トラフ地震とは、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界で100~150年周期で発生している地震で、 主に西日本~東日本の太平洋側に大きな被害をもたらすと言われています。
国が発表している南海トラフ地震の被害想定に宮城県は入っていないので大きな被害は出ないと考えられます。
そのため生き残る宮城県の地域というと、県内全域。
その中でも特に地盤が強く、安全な地域だと言えるのが以下です。
- 青葉区
- 泉区
上記のエリアは東日本大震災の際も被害が少なく、地盤が強いという意見が目立っていました。
もちろん区内でも多少の差はあると思うのですが、東日本大震災のような大きな地震でも被害が少なかったというのは安心できるのではないでしょうか。
もっと詳しく宮城県で地盤が強く安全な地域が知りたいという人は以下の記事を参考にしてみてくださいね。
宮城県で地震が多い理由や液状化の可能性なども調査しています。
南海トラフ地震の震源地が変わったって本当?
南海トラフ地震と聞くと、太平洋側が一気に揺れに襲われる巨大な地震をイメージすると思います。
ですが、最近「南海トラフの震源地が変わった」という噂を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。
これは実際に南海トラフ地震の震源地が変わったわけではなく、震源地が複数現れる可能性があるという意味。
「半割れ」という現象なのですが、南海トラフ地震が発生した際に東側の震源域と西側の震源域がそれぞれ別々に、時間を空けて動くケースが危惧されています。
この半割れが起こると関西の震源地は四国付近、関東の震源地は静岡・愛知付近と、紀伊半島沖を境界として東西に分離することになります。
この場合、震源地がひとつの場合よりも、広範囲かつ大きな被害が見込まれます。
とくに懸念されているのが、2回目の半割れの救助支援が遅れる問題。
そのため、太平洋沿岸の10県(静岡・愛知・三重・和歌山・徳島・香川・愛媛・高知・大分・宮崎)は、1回目の南海トラフ地震が発生してもすぐに他県の応援に行かず、半割れに備えると公表されています。

半割れの可能性があると知っておくだけでも、いざという時に冷静に行動できそうだよね。
南海トラフ地震はどこが危ない?
「南海トラフ地震ではどこの地域が危ないの?」という声が多く聞かれるのですが、主に西日本~東日本の太平洋側が危ないとされています。
その中でも人的被害が多いと言われているのは以下のエリアでした。
| 都道府県 | 死者想定数 |
|---|---|
| 静岡県 | 10万9,000人 |
| 和歌山県 | 8万人 |
| 高知県 | 4万9,000人 |
(参考2):朝日新聞デジタル-南海トラフ地震の被害想定
上記のエリアの共通点としては海が近く、津波の被害が大きいだろうと言われていることです。
すぐに避難できていたとしても、津波で浸水するとライフラインが復活するまでに多くの時間を要します。
避難所での暮らしが長期化することも考えて準備をしておくといいのかもしれませんね。
南海トラフ地震の東北への影響とは
南海トラフ地震では東北への影響はそれほど大きくありません。
建物の倒壊やライフラインが途絶えるといったことはなく、普段通りの暮らしを送ることができると予想されています。
ですが、公共の交通機関の乱れは避けられそうにありません。
とくに新幹線や飛行機に関しては受け入れられない都道府県も出てくるため、移動が困難になることを想定しておきましょう。
南海トラフ地震の宮城県の震度予想
南海トラフ地震が発生したときの宮城県の震度予想は震度3以下と小さなものになっています。(参考3):宮城県-今後予想される地震・災害
また、仙台市などの都心部では東日本大震災以降に建てられた建物の多くにしっかりとした耐震工事がなされていて、地震に強い街作りが進められています。
そのため、万が一予想よりも大きな揺れが来たとしても、安心なのではないでしょうか。
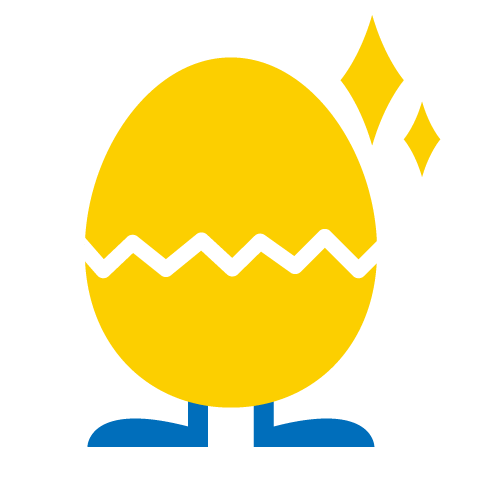
宮城県は地盤の強いエリアが多く、地盤沈下や液状化の危険性が低いのも心強いよね。
南海トラフ地震で宮城県に津波の被害はある?
宮城県に津波が到達した場合に、最も危険とされている津波避難エリア1は県道塩釜亘理線・東部復興道路から海側のエリアで、そこから仙台東部道路・仙台南部道路までは津波避難エリア2に指定されています。
現在のところ、南海トラフ地震の被害想定地域に宮城県は入っていないので、大きな津波は来ないと考えられます。
ですが、念の為に津波が来ても利用できる避難場所などを調べておくのがおすすめ。
仙台市のHPに載っている津波時も利用できる避難場所の一例をご紹介します。
- 仙台うみの杜水族館
- キリンビール
- 中野五丁目津波避難タワー
- 岡田津波避難ビル
(参考4):仙台市-津波避難エリアと避難場所マップ
上記の施設以外にも小学校や中学校は避難の長期化にも対応できる施設として準備されています。
一緒に防災バッグや非常食なども備えておきたいですね。
宮城県・仙台市に地震がくる確率【今後】
今後宮城県・仙台市に巨大地震がくる確率を知りたいという声も多く聞かれたのですが、懸念されている地震はいくつかあります。
1つ目が東北地方の太平洋沿岸で起こるとされている巨大地震なのですが、50年以内の発生確率がほぼ0%とされているので心配はいりません。
2つ目が宮城県沖のプレート間で起こる巨大地震で、30年以内の発生確率が20%ほど、50年以内の発生確率が40%ほどだと言われています。
3つ目が宮城県沖のプレート間で起こる小さめの地震で、こちらは10年以内の発生確率が50%ほど、30年以内の発生確率が90%ほどと注意が必要です。(参考5):仙台市-宮城県沖地震等の発生確率

地震がくる可能性が高いと不安に感じちゃうけど、今からしっかり備えて減災に努めよう。
宮城県・仙台市の地震はまたくる?いつ?
宮城県・仙台市の地震がいつくるのかは上記でご紹介した通りです。
| 地震の場所 | 10年以内 | 30年以内 | 50年以内 |
|---|---|---|---|
| 太平洋沿岸 (巨大地震) |
ほぼ0% | ほぼ0% | ほぼ0% |
| 宮城県沖のプレート (巨大地震) |
9% | 20% | 40% |
| 宮城県沖のプレート (小さめの地震) |
50% | 90% | 90% |
巨大地震に関してはそれほど発生確率が高いわけではありませんが、小さめの地震は避けては通れないのではないでしょうか。
地震はいつ起こるか予測できない災害ですが、前もって備えることで被害を大幅に減らすことが可能です。
例えば、地震で家具が倒れないように固定したり、玄関まで安全に移動できる配置にしたりすることも大切。
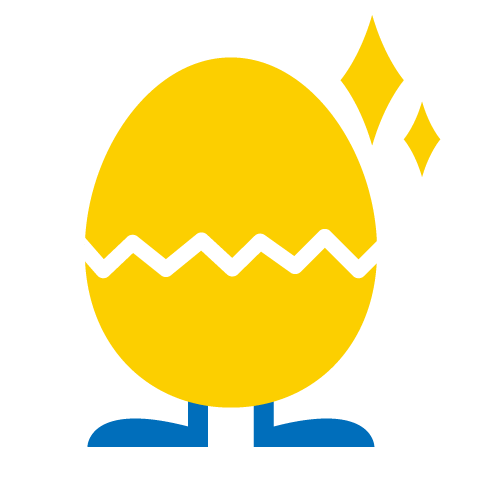
マンションに住んでいる人は長周期地震動で実際の震度よりも大きく揺れるから、家具への対策は必要かも。
まとめ
南海トラフ地震が発生しても宮城県・仙台市は安全なのかや、震度予想などをご紹介しました。
宮城県は全域で被害想定エリア外とされているので、大きな被害はでないと考えられます。
また、仙台市では東日本大震災以降に建てられた建物の多くにしっかりとした耐震工事がなされていて、地震に強い街作りが進められていることもわかって安心です。
この記事を参考にして、大きな地震が来たときのために自分でできる範囲の備えをしておきたいですね。
▼参考にしたページ一覧
(参考1):内閣府防災情報のページ-南海トラフの巨大地震による津波高・震度分布等
(参考2):朝日新聞デジタル-南海トラフ地震の被害想定
(参考3):宮城県-今後予想される地震・災害
(参考4):仙台市-津波避難エリアと避難場所マップ
(参考5):仙台市-宮城県沖地震等の発生確率

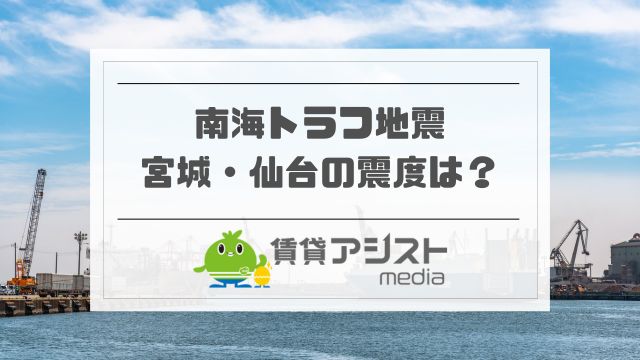



コメント